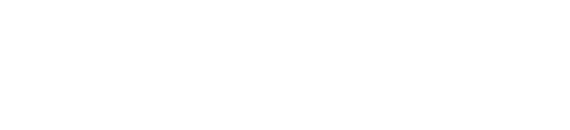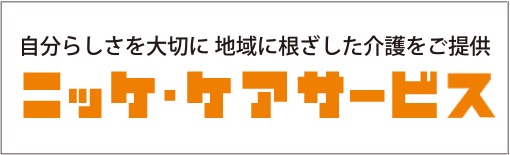Service Flow
介護サービスご利用までの流れ
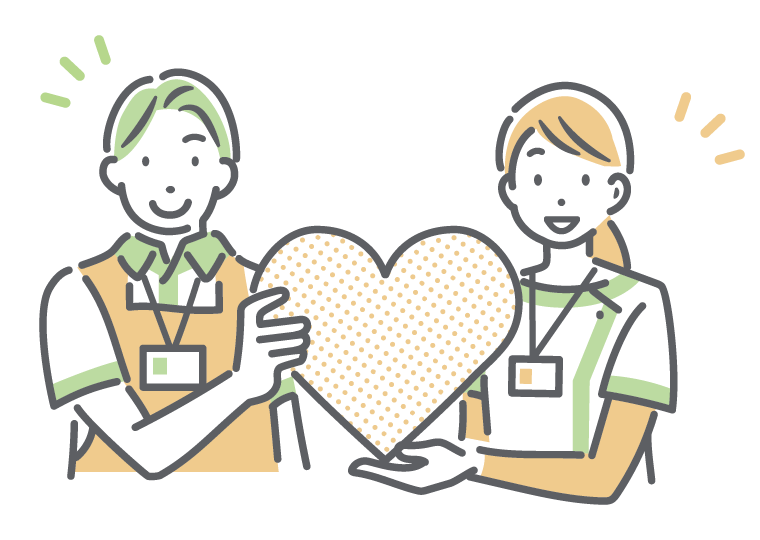
介護保険制度のサービスを利用するためには、「介護が必要である」という認定を受ける必要があります。 お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の申請が必要で、市区町村が要介護度を決定します。要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、要介護度が認定された後は、どのような介護サービスを受けるかをケアマネジャーに相談し、作成したケアプランに基づきサービスの利用が始まります。
-

要介護認定の申請
お住まいの市区町村の窓口に申請するか、または地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに相談すれば申請を依頼することもできます。
-

認定調査
市区町村等の調査員がご自宅を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。市区町村が主治医に主治医意見書を依頼をします。(主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。)
介護認定審査
専門家が、訪問調査の結果や主治医意見書をもとに審査します。
要介護認定
要支援1・2から要介護1~5までの7段階にわかれており、判定結果にもとづき要介護認定を申請者に結果を通知します。(非該当となる場合もあります)
-

ケアプランの作成
「要支援1・2」と認定された方は地域包括支援センターが窓口となります。
「要介護1」以上と認定された方は市町村の指定を受けた居宅介護支援事業者が窓口となります。
-

パムコで提供しているサービス
■居宅介護支援(介護保険申請、ケアプランの作成、介護の相談など)
■訪問介護(ヘルパー派遣)
■福祉用具レンタル・販売
■住宅改修
Q&A
よくあるご質問
-
Q1:介護保険は何歳から使えるの?
A1:65歳から使えます。または40歳以上で特定疾病の人も使えます。●65歳以上の方はすべて対象です。40歳以上(医療保険加入が前提条件)で特定疾病の方も対象で、「要支援や要介護」と認定を受けた方も利用できます。
●病気の後遺症まどで、日常生活に介護の手が必要になったときは、役所・役場の介護保険担当課、病院、身近な介護サービスの事業所などにご相談ください。 -
Q2:介護保険を利用するのに必要なものは?
A2:介護保険サービスを利用するには「要介護(要支援)認定」と「ケアプラン」が必要です。1)役所・役場介護保険担当窓口で介護保険の「要支援・要介護認定申請」を行ってください。
2)要支援・要介護認定の結果、「非該当」「要支援1・2、要介護1〜5」の認定区分が決まります。要支援1以上に認定された方
は、1~3割負担で介護サービスが利用できます。(利用できる上限金額が決められており、その金額にあわせて自宅生活を基
本とした「在宅サービス(通いや短い泊まり、福祉用具レンタル含め)」が利用できます。
3)サービスを利用するためには、「介護サービス計画=ケアプラン」が必要となります。
4)「居宅介護支援事業所=ケアマネジャーの在籍している事業所」と契約して「ケアプラン作成を依頼」することが一般的で
す。(ケアマネジャーに依頼しても利用者に金銭的な負担は一切ありません。)ケアマネジャーはこれからの「みなさんの
相談役・いろいろな調整役」となってくれます。また、ケアプランの自己作成もできます。自己作成用の届出書類は、自治体
に用意されていますので、お住まいの役所・役場にお問い合せください。 -
Q3:介護保険サービスにかかる利用料は?
A3:要支援認定・要介護認定結果に応じた「区分支給限度額」が決められております。●限度額を超えてサービスを利用することはできますが、全額自己負担となります。
●区分支給限度額についての詳しい内容は「介護度区分別利用限度額 | 市川市公式Webサイト」でご確認ください。 -
Q4:ケアマネジャーを探すには?
A4:お住まいの役場窓口や地域包括支援センターで、事業者のリストを配布しています。●ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者はご自分で自由に選択することができます。評判の良いところをご近所で利用している人に聞いて参考にしたり、ネットで公開されている介護サービス情報などを検索してみなさんに合いそうな居宅介護支援事業者を選びましょう。(パムコにもたくさんのケアマネジャーが在籍しております) -
Q5:在宅介護で利用できるサービスは何がありますか?
A5:在宅介護には以下のサービスがあります。●自宅でのサービス
□訪問介護(ホームヘルプ) □訪問看護 □訪問入浴 □訪問リハビリ □夜間対応型訪問介護
□定期巡回・随時対応型訪問介護看護 □居宅療養管理指導 □複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
□福祉用具貸与 □特定福祉用具販売 □住宅改修
●施設に通うサービス
□通所介護(デイサービス) □通所リハビリ □療養通所介護 □認知症対応型通所介護
●短期間の宿泊サービス
□短期入所生活介護(ショートステイ) □短期入所療養介護 □小規模多機能型居宅介護
●介護サービスについての詳しい内容は「厚生労働省ホームページ」でご確認ください。 -
Q6:介護保険負担割合証とは何ですか?
A6:認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」が交付されます。【介護保険負担割合証とは?】
要介護・要支援の認定を受けている方または事業対象者の方は、「介護保険負担割合証(ピンク色ではがき大の証書)」が交付されます。この証書には、介護保険サービスを利用される際の、利用者の負担割合が記載されています。介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証(緑色)とあわせて提示する必要があります。大切に保管してください。
●介護保険法改正により、平成27年8月から一定以上所得者の利用者負担について見直しされ、一定以上の所得がある方の介護サービス利用者負担割合が2割になりました。また、平成30年8月から2割負担者のうち特に所得が高い層が3割負担となりました。
利用者負担の割合 対象となる人 3割 次の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)被保険者本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
・単身の場合340万円以上
・2人以上世帯の場合463万円以上2割 3割に該当しない人で、次の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)被保険者本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
・単身の場合280万円以上
・2人以上世帯の場合346万円以上1割 上記以外の人及び65歳未満の人
【有効期間は?】
介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日~翌7月31日の1年間です。7月時点で介護認定を受けている方には、お住いの市区町村から新年度の介護保険負担割合証が発送されます。
新しい負担割合証が届いたり、負担割合に変更があった際は、担当のケアマネジャーへご連絡お願いいたします。 -
Q7:ヘルパーさんは何でもしてくれますか?
A7:残念ですが、訪問介護は全てのご要望にお応えできるわけではありません。●直接利用者の援助に該当しないサービス(利用者の家族のための家事や来客の対応など)日常生活の援助の範囲を超えるサービス(草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など)ようなサービスを受けることはできません。
●利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
●それぞれの生活状況により受けられるサービスと受けられないサービスがあります。詳しくはご担当のケアマネジャーにご相談ください。 -
Q8:一人暮らしですが、買い物や料理が大変になってきました。お願いできないでしょうか?
A8:ヘルパーによる買い物や料理等の生活支援を受けることができます。●介護保険の認定を受け一人暮らしであれば、サービスを受けることが出来ますが、援助の時間や内容等に利用できる決まりがありますので、ケアマネジャーにご相談ください。また、介護保険のほかに市町村よっては配食サービスを行っているところもあります。 -
Q9:ポータブルトイレをホームセンターで購入する場合も介護保険を利用できますか?
A9:介護保険指定の特定福祉用具業者からの購入が条件となります。●特定福祉用具販売は、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、レンタルになじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施されています。利用者の方のお身体の状態やお宅での設置場所、動線を考慮して選定されることが大事ですので、福祉用具の業者やケアマネジャーに相談し、使いやすい物を選定されることをおすすめします。 -
Q10:介護ベッドや車いすは借りられますか?
A10:認定を受けれていれば1~3割負担で借りられます。●福祉用具貸与の対象は13品目で、要介護度に応じて異なります。車いすや電動で起き上がるベットを借りることが出来るのは「要介護2から5」の認定の方が対象となります。
※「病状が進行したり日々安定しない可能性が著しいお身体の状態にある方」と主治医が必要と認めた方や、要支援・要介護認定調査によって“起き上がりができない”“歩行できない”といった状況が認められる場合などは、要介護1以下であっても、介護保険で借りることができます。
※車いすや電動ベッドにも、いろいろな種類がありますのでお身体や住環境あった製品を福祉用具専門相談員やケアマネジャーと相談しながら選定されることをおすすめします。 -
Q11:実家の親を引き取って介護を考えていますが、手すりをつけることはできますか?
A11:介護保険被保険者証へ記載された住所地での住宅改修工事が対象となります。●介護保険制度工事費用の給付は、工事費全額を支払ってから負担割合に応じた保険の給付を受ける制度ですが、介護保険証に書かれている住所の家を改修する場合にのみ認められますので、実家の親の住所地から引き取り先に住所を変更するなどが必要となります。給付対象になる工事かどうかをケアマネジャーなどの専門家に確認されることをおすすめします。